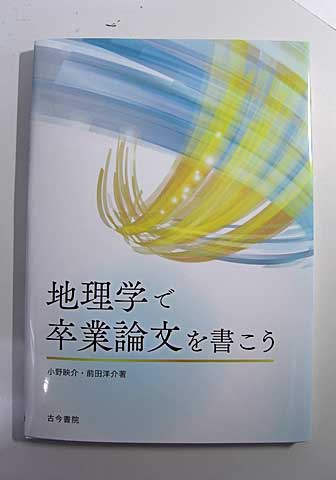下記の通り、竹林景観ネットワーク第33回研究集会&エクスカーションを2024年7月27日~28日に行います。
2024年7月27日(土) 研究発表会・総会(香川大学農学部、対面&オンライン)
2024年7月28日(日) 現地見学会(香川県内のハチク開花跡地ほか、対面のみ)
■総会
日時:2024年7月27日(土)13:30~14:00
場所:香川大学農学部(三木キャンパスDS304教室)、およびZoomを利用したオンライン形式のハイブリッド形式。
■研究発表会
(香川大学農学部先進科学セミナー「タケ類の開花のメカニズムと適応的意義」)
日時:2024年7月27日(土)14:00~16:20
開催方法・場所:香川大学農学部(三木キャンパスDS304教室)、およびZoomを利用したオンライン形式のハイブリッド形式。
参加費:対面500円
○講演
(香川大学農学部先進科学セミナー「タケ類の開花のメカニズムと適応的意義」)
14:00~ 小林 剛(香川大学)
イントロダクション:120年ぶりのハチクの開花から考える植物の有性・無性繁殖の意義
14:30~ 鈴木重雄(駒澤大学), 小林剛(香川大学), 小林慧人(森林総研関西), 久本洋子(東京大学), 福島慶太郎(福島大学), 和田譲二(緑と水の連絡会議)
石見銀山石銀集落跡におけるハチク開花の経過
15:10~ 久本洋子(東京大学大学院農学生命科学研究科秩父演習林)
タケ類の開花までの年数を制御するメカニズムの研究の紹介
○ポスター発表(15:50~16:20)
糟谷信彦*・藤木健太・宮藤久士(京都府大院・生命環境)
ウンモンチクの斑紋の出現タイプ
■懇親会
日時:2024年7月27日(土) 17:30~19:30
場所:三木町 すし富 (15名程度まで)
参加費:5,000円(予定)
■現地見学会
ハチク開花地の更新状況の見学
日時:2024年7月28日(日)9:30-13:00
場所:高松市および東かがわ市を予定(車乗り合いで移動の予定)
(集合場所は、27日に参加者で調整)
参加費:車同乗で移動される場合は、レンタカー代を参加人数で割ります(3,000円ほどを予定)。
【参加・発表申込み】
発表の申し込みの締め切りは2024年7月15日(月)です。懇親会・現地見学会の申し込みは7月20日(土)です。定員に達し次第、閉めさせていただきます。
研究集会への参加は、前日までにお申し込み下さい。準備でき次第、ZoomのURL等をお送りします。
発表形式は対面またはオンラインでの口頭発表形式、またはポスター発表形式とします。口頭発表は、各自のパソコンもしくはタブレット端末でPowerPoint、Acrobat等のプレゼンテーションソフト等の画面を共有して、発表を行っていただきます。発表時間は、質疑を含めて20分程度を予定しています。ポスター発表は、会場壁面に掲出し、ポスター発表時間にディスカッションをおこなえるようにします。いずれも、下記URLよりお申し込み下さい。
※ 一部または全ての口頭発表を香川大学大学院の学生が公聴可能な形式とさせていただきます。公聴をとくに希望しない場合には入力フォーム内でその旨を事前にご連絡ください。
申し込みフォーム
https://docs.google.com/forms/d/1SdM5jSND3UrRN4PpuRDt7RAlGED0SRe6kfq-ylLF-5o